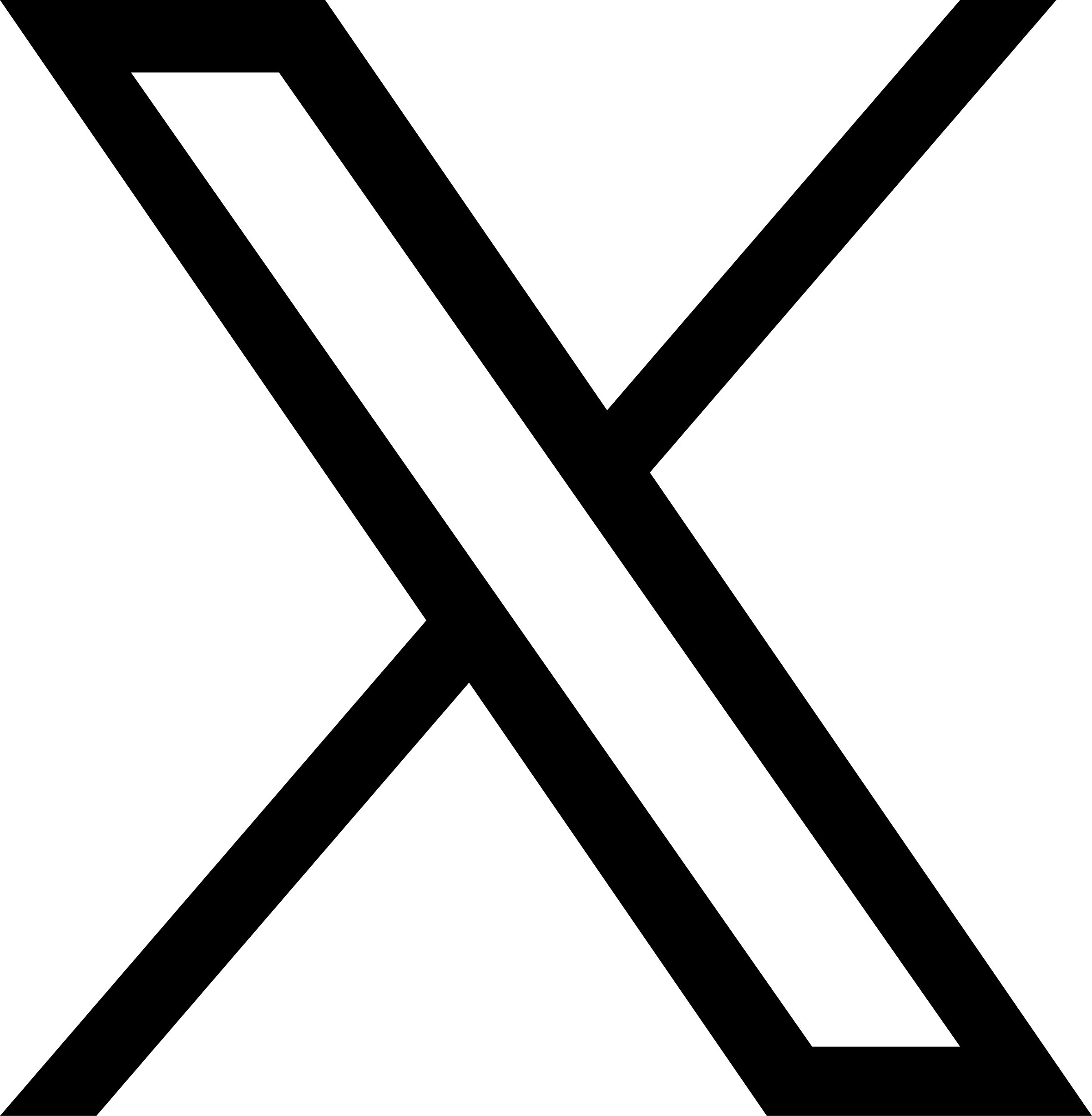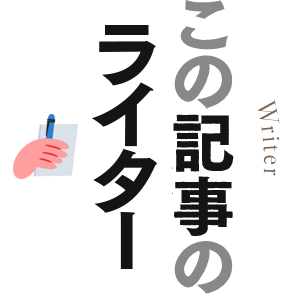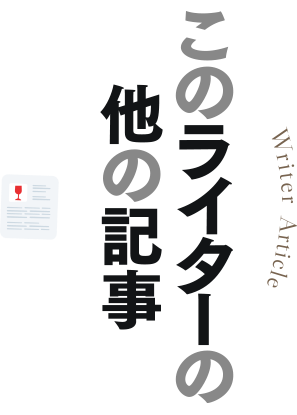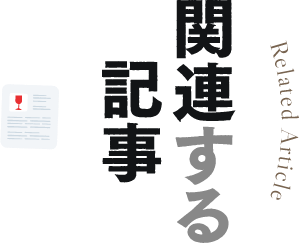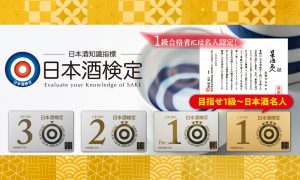日本酒ってどんな酒? Vol.06 「米、酵母による違い ~味はどう変わるの?~」
日本酒の知識

日本酒の商品名に表記されることが多い原料が、米と酵母。詳細にひも解いていくと非常に奥深く、なかなか底が見えません。
なので、これらの原料の違いによって「味わいにどのような違いが生まれるのか」にフォーカスして、種類分けや代表的なものの概要をまとめました。
それぞれ、飲み比べると原料の違いがよくわかる銘柄の一例もご紹介しますよ。
コンテンツ
使用する米のポイント2つ
1. 精米歩合

原料の米において重要なのは、種類だけではありません。
米を表面から多く削ると雑味が取れ、すっきりとした味わいに。逆に精米歩合が高い(=あまり削らない)のであれば、複雑で濃厚な味に仕上がる傾向があるんですね。
同じ種類の米でも、精米歩合を変えるとかなり違った特徴を持つ酒になるのも、日本酒の面白いところなんです。
2. 米の品種

今回は、こちらをメインに見ていきましょう。酒造りに適した品種「酒造好適米」は、一般的には朝晩の寒暖差が大きい土地でよく育つため、標高の高い山間部でさかんに栽培されています。
品種選びは、どんな酒に仕上げたいかというコンセプトに大きくかかわってきます。複数種をブレンドして用いることも多いのは、ワインとも似ていますね。仕込み水との相性なども考慮されます。
では、ここからは代表的な酒造好適米4つの特徴を、ざっくりと見ていきましょう!
- ① 山田錦
-
「酒米の王様」と賞される。総生産量は断トツトップで、兵庫県がその約6割を占めます。大粒で、心白(=米の中心)が適度な大きさ、雑味の元となるタンパク質含有量が少ない、という酒造りに適した特徴を多く併せ持っているんですよ。香り高く、バランスの取れた酒に仕上げられる傾向があります。
- ② 五百万石
-
新潟県発祥の品種。国内の最も多くの地域で栽培されています。心白がかなり大きく、50%以上削るのが難しいため、純米大吟醸酒・大吟醸酒に使われることはあまりありません。少し水に溶けにくいという特性から、淡麗辛口の酒によく採用されています。
- ③ 美山錦
-
1978年に長野県で生まれた、代表的な品種の中では比較的新しい酒米。寒さに強く、長野県だけでなく東北や北関東、北陸でも栽培されています。こちらは心白があまり大きくなく、たくさん削ることが可能なので純米大吟醸酒・大吟醸酒にも重宝されます。キレのある、すっきりとした味わいに。
- ④ 雄町
-
1859年に岡山県で発見された品種を、改良して栽培。山田錦や五百万石をはじめ、現存する約3分の2の酒米の先祖とも言われています。大粒ですが心白も大きいので、精米歩合が低い酒には向きませんが、芳醇かつ、深いコクのある酒に仕上げられます。
米の違いが楽しめる銘柄の例
ここでは「風の森 807シリーズ」を挙げてみました。精米歩合が高く、米の力強さが感じられるシリーズです。微発泡があり、フルーティーなニュアンスも感じられるので、日本酒にちょっと苦手意識がある方でもトライしやすいと思いますよ。

風の森 807シリーズ
■油長酒造 公式サイト(https://www.yucho-sake.jp/kazenomori/)
酵母は特に、香りの決め手に

もうひとつ、商品名に原料の名前がつく機会が比較的多いのが「酵母」。しかし米よりはその頻度が低いので、ここでは概要をさらりとなぞるだけに留めます。
アルコール発酵に欠かせないのが酵母ですが、発酵の際には、アルコールだけでなく、味や香りに関わる成分がたくさん生み出されるんですよ。
では、酵母の違いによって仕上がりにどのような影響が出るのか。おもに下記の3点と言われています。
- ① 香り
-
酵母による影響が最も大きいとされているのが、香り。リンゴやバナナを連想させる、吟醸造りによるフルーティーな「吟醸香〔ぎんじょうか〕」をはじめ、酵母は、香りの種類や強弱を決める要因となります。
- ② 深み
-
酵母には、「泡あり酵母」と「泡なし酵母」があります。おもに発酵力の強さで分けられていて、この違いによってアルコール度数や副産物の量・質が変わり、酒の深みに影響します。
- ③ 濃淡
-
上記と少し似ていますが、こちらは淡麗か濃醇か、だととらえてください。言い方を換えると、すっきりかしっかりか、にも酵母の影響が出るということです。
酵母の種類

花から採れる、花酵母も日本酒に使われます。
協会系酵母
日本醸造協会が頒布〔はんぷ〕。協会系酵母には、“6号”と“601号”のように、先述した泡あり・なしが同じ番号で両方存在するものもあります。
最も多く採用されているのが「協会7号」で、発酵力の強さと華やかな香りが特徴。そのほか、香りは抑えめで、まろやかかつ淡麗な酒に向く「協会6号」などがあります。
6号酵母は「新政〔あらまさ〕酒造」、7号酵母は“真澄”の銘柄で知られる「宮坂醸造」がそれぞれ発祥。これらの酒を飲み比べてみると、酵母の違いがイメージしやすいかもしれません。
自治体開発酵母
各都道府県の自治体が開発した米とセットで、よく用いられます。さらに水も含めて、その土地のカラーが色濃く反映されます。
花酵母
その名の通り、花から分離させて採取された酵母。発酵力が強く、花の種類によって異なる豊かな香りが特徴です。
自家酵母
酒蔵に自生、つまり棲みついた酵母ということで、「蔵付き酵母」とも呼ばれます。協会系酵母に比べて培養や品質の安定が難しくはありますが、ほかにはないオリジナリティを打ち出せるので積極的に活用する酒蔵も。
酵母の違いが楽しめる銘柄の例
たとえば下記。精米歩合や仕込み方法などを統一して、酵母だけ変えた商品をなんと6つも飲み比べできるんです! これほどの種類は珍しいですが、酵母の違いを打ち出した商品は各蔵で時々見られるので、チェックしてみると面白いですよ。

■土田酒造 公式オンラインショップ(https://cart.homare.biz/i/SS0069)
次回からは「造り」による違い!

それぞれの違いは、やはり飲み比べて実際に体感するのが一番。特に米は、品種による違いを押し出した銘柄がさまざまな酒造からリリースされているので、見かけたらぜひ試してみてくださいね。
次回からは、「造り」による違いに迫っていきます!
日本酒ってどんな酒?
|