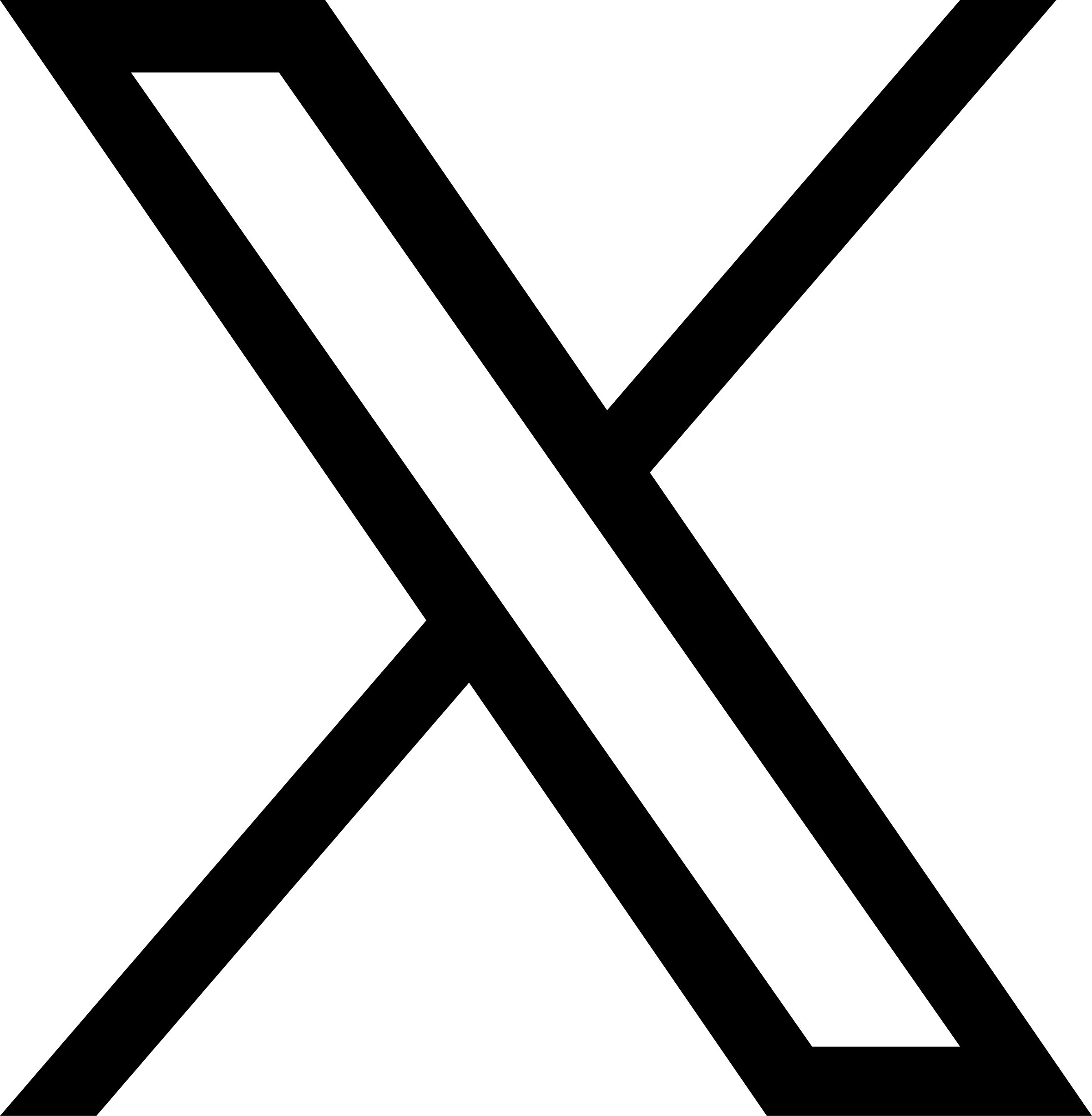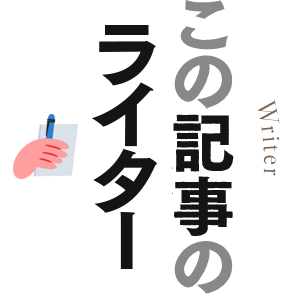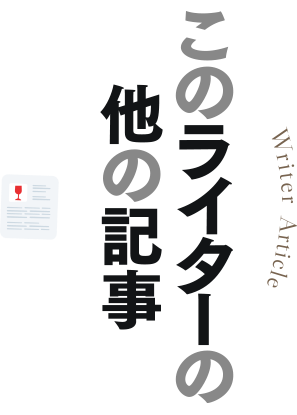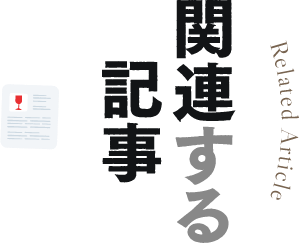ビールってどんな酒? Vol.09 「“苦い”のに、なんで“美味しい”の?」
ビールの知識

今回は予告していた通り、初心者が一度は行き当たる「ビールは苦いのに、なんで大人は美味いと言うのか」に迫ります。そこがいいんじゃない! と手放しに喜んでいた人も、読んでいただければ苦みが一層好きになる、かも。
コンテンツ
苦みは危険感知センサー

元々は「苦い=毒」だった
まずお伝えしたいのが、苦みに対して嫌悪感を覚える反応のほうが、ある意味で正常であるということ。え、じゃあビールをウマいウマい言うて飲んでる人の感覚は異常なのか・・・? というとそういうわけでもなくて。
苦みは人間にとって、先天的には美味しいと感じる味覚ではないんですね。どういうことかというと、元来苦みは、食物の危険性(毒性)を感知するためのセンサーとして生物に備わった、とされているんです。
つまり、苦みが美味しさに変わるためにはまず、「この食べ物は安全なんだ」と脳が理解する必要があるというわけ。ひと言でいうと、「慣れ」が必要ということですね。
子どもは大人の3倍味覚が敏感

もう一つ。大人になるにつれて、味覚が鈍感になるのも関係しています。舌の表にある味を知覚するセンサー「味蕾〔みらい〕」は、一定の年齢を過ぎると減少していき、30~40代になる頃には約1/3になると言われています。
ビールも「大人の味」と表現されることが多いですが、そのほかにも酒のつまみや珍味には、苦みや酸味、塩辛さなど刺激が強いものがたくさんありますよね。
簡単に言うと、味覚が鈍感になるから、苦みを美味しいと感じられるようになるのです。子どもの頃あんなに嫌いだったピーマンが、久しぶりに食べてみると案外食べられた、という例に心当たりのある方は多いでしょう。
苦みには良いこともいっぱい!

食欲増進など効能いろいろ
「鈍感になって慣れること」。これだけを書くと、なんか労働みたいですね・・・。そうまでして苦みを味わう必要ある? という声が聞こえてきそうです。もちろん、苦みが心身におよぼす良い影響はいろいろとあるんですよ。
ビールのホップには「イソフムロン」という成分が多く含まれていて、これが苦みのもとと言われています。この成分は、ホルモンバランスを整えるとされていて、脂肪の代謝も促進してくれます。腸内寄生虫への予防効果もあり、腸内フローラを整える働きも期待できます。
さらに、苦みの刺激自体が唾液の分泌を促すので、消化機能も活性化するんですね。「適度なビールは、食事をより充実させる」と言えるでしょう。
ストレス解消効果も!?
また、苦みには「抗ストレス作用がある」という説もあるんです。仕事の後のビールがとにかくウマいのは、心身がストレスを抱えているときほど苦みを美味しいと感じる構造があるから、という一因がありそうです。もちろん、炭酸のスカッとした爽快感もひと仕事終えた後にはたまりませんけどね。
「良い苦み」に出会うこと

苦みは一つじゃない
苦いだけの味わい、というのは基本的に存在していません。そこに多彩な香りや甘み、炭酸の刺激が加わるからこそ、ビールは美味しいのです。苦み自体も一種類ではなく、グレープフルーツのようなフレッシュ感があったり、樹脂のようなウッド系のニュアンスがあったりとさまざま。さらに、本来は渋味であるものを苦みと勘違いする、ということもあるようです。
「苦みが少ないビール」を試してみて

というわけで今回の結論。「良い苦み」に出会うことが、苦みを美味しいと感じられるようになるための最善の道です。
日本人のビール嫌いは、大多数の人がピルスナーから入るから、だと思っています。ピルスナーって、数あるビアスタイルの中でもかなり苦みが際立ったスタイルなんですね。だから、ビールの苦みがどうも好きになれない、という方は、「フルーツビール」「ヴァイツェン」「ニューイングランドIPA」あたりのビアスタイルをぜひ一度試してみてください。
クラフトビールを何種類か置いている店で、「あんまり苦いのが得意じゃなくて」とはっきり伝えて、おすすめを提供してもらうのも良いと思います。
ビールについて造詣が深い人ほど、ビール=苦い、だけではないということを知っているので、きっと印象ががらりと変わるような一杯を出してくれますよ。そこから徐々に、苦みに慣れていけばいいのです。
次回は「ビールの味わい方」について
以上のことをふまえて、次回はビールの味わい方、「ビア・テイスティング」について解説します。
喉を目がけて流し込むだけではもったいない! どうやったらビールの魅力をより深く堪能できるのか。ぜひご期待ください。
ビールってどんな酒?
|